NHKスペシャル「モノ言う株主」を観て、強く印象に残ったのは、
「市場のおまわりさん」として経営に切り込むアクティビスト株主の存在だった。

番組では、カナメキャピタルのパートナーが「株主から預かったお金をネコババする経営者がいたら、それは懲らしめなければならない」と強い言葉で語っていたけれど、正直なところ、私は「ずいぶん偉そうなことを言う人がいるものだな」と感じた。こうした強硬なスタンスは、日本企業の文化とは少し相容れないところがあるのではないか、というのが率直な印象だ。
けれども、そうしたアクティビストの存在が、まったくの異物かといえば、そうとも言い切れない。例えば、番組内で取り上げられていたフジメディアホールディングスの事例のように、大株主が経営に深く関与し、ガバナンスにメスを入れる動きは、確かに今の時代の一つの潮流なのだと思う。
経営の透明性や説明責任を強く求められる中で、企業が「見られている」という前提で動くことは、決して悪いことではないのかもしれない。投資ファンドが経営に対して成長戦略の提案を行う。それが受け入れられなければ、株主代表訴訟などの非友好的な手段に訴えることもある。こうした背景には、アベノミクスによる海外資本の流入があり、経営と株主との関係が大きく変わってきたことがあるのだろう。
私自身の会社も、ここ1年で大きく変化してきたと感じている。というのも、私たちは親会社のもとで経営が行われており、ここ最近はその親会社からの介入が格段に強くなってきている。会議体の構成が変わり、人事の決定にも明らかに親会社の意向が強く働いている。現場としては、その理由や背景がよく見えないまま指示が降ってくるので、戸惑いを感じる場面も少なくない。一部の社員からは、「まるで植民地のようだ」と揶揄する声も聞こえるが、私は資本関係に基づいた当然の統治だとも、最近は思っている。
そうした親会社の介入もまた、さらにその上にある株主からの圧力を受けての行動なのではないかという視点もある。親会社も、上場企業である以上、株主からの期待や要求に応えなければならない。企業価値を高め、持続可能な経営を目指すために、グループ全体の効率や透明性を高める必要がある。その一環として、私たちの会社にも改革の波が押し寄せているのだと考えれば、少しは納得がいくような気もする。
こうして自分の会社の状況を改めて考えてみると、実は今の日本企業全体が直面しているガバナンス強化の流れの中に、自分たちもいるのではないかと思い至った。
NHKの番組で紹介されていたように、従来の株主総会は経営者に対する形式的な承認の場だったが、今や株主が経営にNOを突きつけることも当たり前になっている。
そしてそれに伴い、企業も変わらざるを得ない時代に入っているのだろう。
経営にとっては厳しい時代かもしれないが、これは企業が本来持つべき責任を改めて問われているのだともいえる。
もちろん、投資ファンドの介入が企業価値を向上させる可能性はある。
ただ、それによって私たちの生活が良くなるのか、社会全体が豊かになるのかという点には、疑問が残る。
経営の効率化、利益の最大化だけを追求するなかで、社員の働きがいや長期的な社会的信頼といったものがないがしろにされないか。それは私たち一人ひとりにとって、決して無関係な話ではない。企業というのは、単に数字を積み上げる場所ではなく、そこに集う人々が安心して働き、価値を創造し、持続的に成長していく場であるべきだと思う。
株式会社の仕組みや市場というのは、改めて考えると本当に興味深い。誰がお金を出して、誰が経営して、誰がその成果を受け取るのか。そしてその中で、私たち働く人々の位置づけはどうなっているのか。数字で評価される資本市場の論理と、現場で働く人間のリアルな感情や生活との間には、大きなギャップがある。それをどのように埋めていくのか、あるいは埋められるのかは、これからの企業経営にとって重要なテーマなのだろう。
番組に出演していた取締役協会の富田氏と、首藤教授の話が全然かみ合ってなかったし。
【取締役協会】https://www.jacd.jp/
NHKスペシャルをきっかけに、そんなことをじっくりと考えさせられた。変化の真っ只中にいるときは、ぎすぎすしたり、疲弊したりすることもある。
それでも、企業がよりよくあるために、自分たちがどういう立場で何を感じているのかを言語化しておくことは、必要なのではないか。
言葉にすることで、目の前の現実を少し客観視できるし、仲間と分かち合うこともできる。
そんな思いで、このブログを書いてみました。読んでくださった方が、何かを感じ取ってくだされば幸いです。

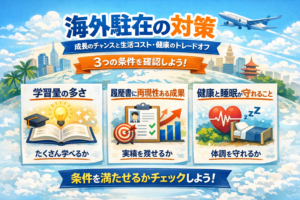


コメント