職場に、イタリア駐在経験者がやってきた。
イタリア語はどうだったのですか?なんて話しました。
その人は、語学学校に通うのではなく、コミュニティの無料イタリア語講座に通っていたらしい。
そこには、自分よりもはるかにイタリア語を喋れる人がいて、主にアフリカ大陸から出稼ぎにイタリアに来る人だという。なんで、語学教室にくるのだろうというくらい、流ちょうなイタリア語を話すのだという。かたや自分はまったくイタリア語のバックグラウンドもなしにイタリアにいったので、よちよちのイタリア語で話していた。
しかしながら、読み書きのテストになると違うのだという。
イタリア語を喋れない自分は読み書きテストで高得点をとれるのに、アフリカ系出稼ぎ人は、0点なのだという。その人は、そのような光景を目の当たりにして、日本の語学教育に感じるものがあったのだといいました。
★★★
その人がどのようなことに「感じるものがある」と思ったのかは突っ込めませんでした。
和やかなランチの場所でしたし。
想像するにこの話は、「日本の語学教育は、読み書き能力に重きを置きすぎていて、コミュニケーションができないから改革すべきだ」ということになるのだろうか。
今の日本の風潮からすると、そうなのかもしれません。
しかし、わたしはそうは思わないのでした。その人たちは、イタリア語でコミュニケーションができるけれども、文書を読むこと書くことができない。もちろん、まんべんなくできることが理想ではあるものの、得意も不得意も、語学に注げるリソースも違う。
そこで、この文章を思い出したのでした。読み書きよりも、オーラルコミュニケーションに重きを置くのは、植民地政策の宗主国の考え方であって、そんなのに騙されんなよ、って言っているように思える。
「グローバル・コミュニケーション」と言っても、オーラルだけが重視されて、読む力、特に複雑なテクストを読む能力はないがしろにされている。これは植民地の言語教育の基本です。
植民地では、子どもたちに読む力、書く力などは要求されません。オーラルだけできればいい。読み書きはいい。文法も要らない。古典を読む必要もない。要するに、植民地宗主国民の命令を聴いて、それを理解できればそれで十分である、と。それ以上の言語運用能力は不要である。理由は簡単です。オーラル・コミュニケーションの場においては、ネイティヴ・スピーカーがつねに圧倒的なアドバンテージを有するからです。100%ネイティヴが勝つ。
逆に、植民地的言語教育では、原住民の子どもたちにはテクストを読む力はできるだけ付けさせないようにする。うっかり読む力が身に着くと、植民地の賢い子どもたちは、宗主国の植民地官僚が読まないような古典を読み、彼らが理解できないような知識や教養を身に付ける「リスク」があるからです。植民地の子どもが無教養な宗主国の大人に向かってすらすらとシェークスピアを引用したりして、宗主国民の知的優越性を脅かすということは何があっても避けなければならない。だから、読む力はつねに話す力よりも劣位に置かれる。「難しい英語の本なんか読めても仕方がない。それより日常会話だ」というようなことを平然と言い放つ人がいますけれど、これは骨の髄まで「植民地人根性」がしみこんだ人間の言い草です。
http://blog.tatsuru.com/2018/10/31_1510.html
さて、今は建前的には植民地はないことになっている。そんななか、言語を学習するということは何か。
僕自身はこれまでさまざまな外国語を学んできました。最初に漢文と英語を学び、それからフランス語、ヘブライ語、韓国語といろいろな外国語に手を出しました。新しい外国語を学ぶ前の高揚感が好きだからです。日本語にはない音韻を発音すること、日本語にはない単語を知ること、日本語とは違う統辞法や論理があることを知ること、それが外国語を学ぶ「甲斐」だと僕は思っています。
http://blog.tatsuru.com/2018/10/31_1510.html
内田樹先生、こんなに引用しまくってごめんなさい。。。
こんなことを言うのって、現実的ではないのかな?現実問題、人が語学ができなくて困る場面は、ほとんどの場合対面で話しているときですから。
でもさ、語学を学ぶ目的が「格付け」「社会的地位」でなくその「文化」であり異文化に対する知的好奇心を満たすものであるのであれば、日本語を学ぶ外国人というのは、とてもその潜在的なポテンシャルというのはあるんじゃないですかね。東南アジアの人々であれば違いますが、
文化に対する好奇心って、わたしは持っているのでしょうね。とおもうのでした。

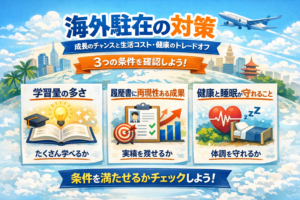


コメント