第1章:目覚めのルーティン
午前5時55分、カイの寝室にやわらかな光が差し込んだ。
自動カーテンが静かに開き、朝日の波長を模した照明が、部屋の空気をあたためる。
彼はまだ眠っていたが、左手首に巻かれた睡眠管理デバイス〈SOMNO-11〉が、起床タイミングを判断していた。
深部体温、呼吸数、脳波の揺らぎ。全身のリズムを読み取ったうえで、最も“整った”目覚めの瞬間が選ばれる。
「起床スコア:83」
「深睡眠:3時間18分」
「覚醒バランス:安定」
カイのまぶたがゆっくりと開いた。
意識が静かに浮上してくる。
目覚めたときの感覚──重すぎず、軽すぎず、ちょうどいい“自分”がそこにいる。
シャワーを浴びたあと、α-トリプトシェイクを一口。
朝に摂ることで、夜のメラトニン合成が促される。
キッチンのAIアシスタントは、今日の快眠維持スケジュールを提示してきた。
「本日も整った一日を。日没は18:04。理想入眠時間は21:36です」
朝食は、“消化負担指数”をもとに調整されたプレート。
味よりもリズム。カロリーよりも恒常性。
すべては、夜に向けての“予備睡眠”の一部だった。
外に出ると、街全体がゆるやかに動いていた。
車の音もなく、看板も静かに光を落とすだけ。
騒音もネオンも、この時代には存在しない。
“活動”はすべて朝に集中している。
夕刻には街全体が穏やかに沈み、夜は“社会全体が眠る時間”として厳密に管理されていた。
通勤列車のなかでは、乗客のほとんどがイヤホンで“入眠サブリミナル”を聴いていた。
夜の眠りに備えるため、朝から副交感神経を整える。
カイもまた、自動的に再生される波音に耳を傾ける。
ふと窓を見やると、今週の「スリーパー・オブ・ザ・ウィーク」の顔がビルのスクリーンに映っていた。
快眠スコア97。深睡眠4時間半。社会的評価上位1%。
その人物が言う。
「眠りは、最も賢い選択です」
カイは、ただ黙って目を閉じた。
この世界では、眠りこそが自己管理の最終形とされている。
眠れないことは、自己制御の失敗とみなされる。
だから人々は、今日もよく眠るために、朝を選ぶ。
彼もそうだった。
——ただ、最近になって、ふと、思うことがあった。
「夢って、スコアに入っていないよな」と。
その問いが、静かに彼の中に残ったまま、列車は無音の駅に止まった。
かつて、人々は眠りを軽んじていた。
成功のために、自己実現のために、学び、働き、戦い続けることが美徳とされた時代。
1日4時間睡眠で働くCEOは称賛され、徹夜明けの若者が「努力の証」としてメディアに取り上げられていた。
その代償は大きかった。
鬱病、不安障害、認知機能の低下、免疫異常。
静かに崩れていく社会の底に、常に**「眠らないこと」**が横たわっていた。
21世紀半ば、ある転機が訪れる。
睡眠科学の飛躍的進展により、人類は気づいてしまったのだ。
**「眠りは、ただの休息ではない」**ということに。
それは、記憶を統合し、感情を整え、免疫を強化し、創造性を再起動する、人体の中枢的な知的営みであった。
そして何より、「よく眠る人間は、病まない」「社会は安定する」という確かなデータが、人々を動かした。
政府は「国民快眠戦略」を打ち出し、
企業は「睡眠スコア報酬制度」を導入し、
学校では「睡眠訓練」と「夢の記録」が必修科目となった。
社会は、こうして再設計された。
すべての建築、制度、経済活動、文化、娯楽までもが、**「より深く、より質の高い眠りを得るために」**最適化された。
人類はついに、朝を中心とする生活様式に辿り着いたのだ。
これが、「快眠至上主義」と呼ばれる時代である。
——眠ることを最も大切にすること、それは、人間であり続けるための最後の知恵だった。



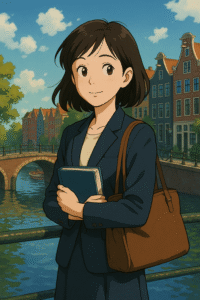
コメント