見抜けなかった場所
私が会社を辞めることになった、と告げたとき、思ったより多くの人が驚いた顔をした。
驚かれるほど、私はこの場所に必要とされていたのだろうか、と一瞬だけ考えたが、その考えはすぐに消えた。
「どうして?」
「どこに行くの?」
「もったいないよ」
同じ言葉が、少しずつ違う声色で繰り返された。
私は用意していた答えを口にした。
「転職するんですよ。待遇が良くて。年収3000万円でわたしを雇ってくれるみたいなんです。」
それ以上の説明はしなかった。
本当の理由を話すほど、ここに期待していなかったからだ。
この会社で、私はずっと“役に立つ便利な人”ではあった。
けれど、“伸ばすべき人”として扱われたことは、一度もない。
私は秘書として、同じ仕事をずっとしていた。
正確には、「同じ仕事だけを」していた。
社長の予定を管理し、食事の好みを覚え、気分の波を先回りして整える。
誰もやりたがらない細かい雑事は、いつの間にか私の仕事になっていた。
社長は気分の波が大きく、社内でも面倒な人として扱われている。パワハラのバリバリ営業系。
確かにすごいところもあるけれども、組織のトップに立つようなひとではない。
それでも、政治的な権力関係から社長の座についている、と私は理解している。
面倒な社長の世話をしている私がいる一方で、
活躍の場を海外に移す人は、次々と名前を呼ばれていた。
「若いうちに経験させたいから」
「チャンスがある人に行ってもらわないと」
いつのまにか、そういう人が増えていた。
私はそのたびに、自分が“若くもなく、チャンスもない側”に分類されていることを理解した。私だって同じチャンスを得ているはずなのに、というのは幻想だったんだ。そう、失望した。
秘書だから。
手放すと困るから。
そういう思惑で、ずっとこの仕事をしている。
それは評価ではなく、固定だった。
誰も「やりたいか」とは聞かなかった。
「できるよね?」とだけ言われた。
できることが増えるほど、仕事は広がらず、重くなった。
秘書は治外法権、聖域の仕事。
多めに見てもらっている部分が多いとは思っているけれども、だからこそ誰も口出ししてこない。放置されている気がした。見捨てられている気がした。とりあえず、社長の逆鱗に触れないように置かれている立場な気がしていた。
上層部の顔色を見て、うまくやれる人間だけが、そこにアサインされて閉じ込められる。
私の周囲には、いつの間にか“代わりがいない仕事”だけが積み上がっていた。
かわいそうだね、と言われたことがある。そんな仕事に閉じ込められて。やりたくてやっているわけではないのにと。
同情はあったが、提案はなかった。
私は哀れまれるほど、無力ではなかったはずだ。
我慢できなかったのは、忙しさではない。
役割が与えられ続けることでもない。
仕事ができないと思われているのに、
仕事ができるかどうかを試される場所すら与えられないことだった。
私も私だ。いやだったら嫌だといえばいいのに、自分の性格もあり、そうは言えなかった。だから、もう限界を感じていた。
「待遇が良くて」
そう言ったとき、私は嘘をついた気はしなかった。
年収は三千万円になる。事実だ。
条件も、裁量も、これまでとは比べものにならない。
けれど、それが理由のすべてではないことも、わかっていた。
「それだけ?」
誰かが、少し笑いながら聞いた。
私はうなずいた。
説明を足せば足すほど、この会社に対して誠実になってしまう気がした。
幻滅した、と言うのは簡単だった。
活躍の場所がない、と言えば、少しは理解されただろう。
でも、それを言葉にする義務は、もう感じていなかった。
この会社が私を見抜けなかったことよりも、
私がこの会社に期待していた時間のほうが、ずっと長かった。バカだったのだ、わたしは。そう思えてしまう。自分にほかの人と同じだけチャンスがあったか?そんなバカな。
だから、最後くらいは、何も求めずに去りたかった。
理由を説明し、理解を求め、反省を促すほど、私は親切ではなかった。
「待遇が良くて」という言葉は、
相手を責めずに済む、最も無難な理由だった。
そして同時に、
ここでの評価が、私の価値の上限ではないと示す、唯一の数字でもあった。
その数字を聞いた瞬間、
いくつかの表情が変わった。
驚き。
計算。
そして、納得。
ああ、と思った。
人は理由よりも、金額で人の選択を理解するのだ。
私が去る理由を、
誰も「環境」だとは考えなかった。
それでよかった。
見抜けなかったのだから、最後まで気づかなくていい。
転職してから、私はマンションを購入した。
眺望がいいわけでも、誰かに自慢できる場所でもない。
ただ、鍵を回したときに、ここは私の判断で選んだ場所だと思える部屋だった。
住宅ローンの残高と、金融資産の一覧を並べると、
合計は一億円に、もう少しで届くところまで来ていた。
その数字を見ても、胸が高鳴ることはなかった。
むしろ、静かだった。
ああ、私はここまで、自分の力で来たのだと、
ようやく認めてもいい気がした。
年収が三千万円になったから、
マンションを買えたわけではない。
買ってもいい、と自分に許可を出せるようになっただけだ。
ここで働いていても、
きっと私は、同じ選択はしなかっただろう。
いつ異動になるかわからない。
いつ代わりが現れるかわからない。
そう思わされ続ける場所では、
長期の決断はできない。
休日に、カーテンを開けて、部屋に入る光を眺める。
急ぐ理由はない。
将来の不安が消えたわけではないが、
不安に支配される必要もなくなった。
資産があるということは、
贅沢ができるというより、
選択肢を奪われない、ということなのだと知った。
あの会社にいた頃の私は、
ずっと「今」をこなすためだけに生きていた。
今は、ようやく、
少し先の未来を前提に、今日を使っている。
久しぶりに、元同僚から連絡が来た。
近況報告というほどのものでもなく、
ただ「元気?」とだけ書かれていた。
何度かやり取りをしたあと、
ふと、こんな一文が送られてきた。
「最近、すごいところにいるって聞いた」
私は画面を見つめて、しばらく考えた。
すごい、という言葉が、どこを指しているのかが、わからなかったからだ。
会社の名前だろうか。
年収の数字だろうか。
それとも、もう戻らなくていい場所から、ちゃんと離れたことだろうか。
「そうでもないよ」
そう返して、会話はそれ以上続かなかった。
それで十分だった。
私がどこにいて、何を得て、
何を失わなかったのかを、
説明する必要は、もうなかった。
見抜けなかったのは、私ではない。
ただ、それを確かめる場所が、
ようやく変わっただけだ。
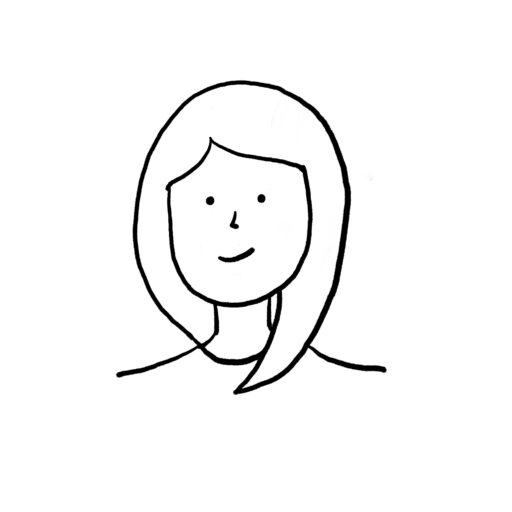


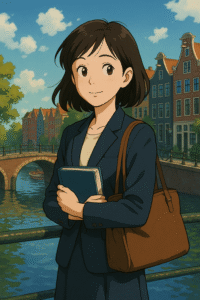

コメント