私たちはよく、「言葉は大切だ」と言います。
誰かを慰めるひと言、何気ない表現が誤解を生んでしまったとき、言葉の力を強く実感します。
たった一言の言葉に救われたことは何度もあるし、傷ついたことも何度もある。
「心無い一言」なんて、よくある話です。
だからこそ、言葉を丁寧に使おう、相手に配慮して話そう、そう心がける人も多いのではないでしょうか。
私自身も、そうした思いで日々の言葉と向き合おうと、思っています。
もちろん、そうでない時も多いですが…反省することも多いですが…
NHKで放送されていた『舟を編む』というドラマを見たとき、その気持ちはさらに深まりました。辞書を編むという、非常に地道で誠実な仕事に携わる人たちの姿が描かれるこのドラマです。
一語一語を、どのような意味で、どのような文脈で定義するかを、丹念に考え続ける彼らの姿に、私は心を打たれました。そして、言葉の持つ一言一句、相手がどうとらえるか。言葉を大切にするとは、こういうことなのか、と深く感じたのです。
けれども同時に、ふと考え込んでしまったことがあります。
私たちは「丁寧な言葉」「美しい日本語」を当然のように良いものと感じて、言葉のとらえ方を考えていますが、
その価値観は本当に、誰にとっても自然で共通のものなのでしょうか?
たとえば、私の職場には外国籍のパートナーと暮らしている同僚がいます。
家庭では英語での会話が中心のようで、日本語の表現がやや直訳的でストレートに聞こえることがあります。
そうした話し方が、日本語文化の中では「少し配慮が足りない」と受け取られてしまう場面もあるのですが、
彼女自身はとても誠実で、真っ直ぐな心を持った人です。
帰国子女の同僚もいます。正直、彼女の日本語のレベルは稚拙だと感じざるを得ません。高校生までは漢字が読めなかった彼女。言葉を話している分には問題ないけれども、書き言葉になると下手なのです。ぶっきらぼうに感じる、説明が足りないと感じる。でも、彼女はそれの何が悪いかはわからない。
言葉の足し算と引き算は、人によってバランスが良いと感じるものは違うのです。ある人は、「言わないとわからないから」と言葉を足していき説明しすぎだと感じられてしまいます。ある人は「無駄を省いて効率重視の言葉を使用」して、言葉をひいていき、結果として説明不足に感じる。
どちらも顔を合わせている同僚なので人柄そのものは知っているし、文章から受ける印象とは全然違います。
このように、「正しい言葉づかい」ができないからといって、その人の人柄まで評価してしまうのは、どこか違う。
言葉をどう使うかは、その人の性格だけでなく、育ってきた環境や文化的背景に大きく影響されます。
どんな言語に囲まれて育ったのか、どんな教育を受けてきたのか——そういったことが如実に表れるものです。
文章では感情をうまく表現できなくても、対面では相手の目を見て、丁寧に話すことができる人。
そういう人も、たくさんいます。
だから私は、「言葉が荒い」「言い方が変」と感じたとき、
すぐに「この人は感じが悪い」と判断するのではなく、
「どうしてそう話すのだろう?」と背景に思いを馳せるようにしています。
言葉を大切にすることは、人と人とをつなぐうえで、とても大切です。
けれども、その「美しさ」「正しさ」が、いつの間にか「基準」や「評価」になってしまったら、
それは誰かを静かに排除する「壁」にもなり得るのではないでしょうか。
私は、日本語が好きです。
四季の移ろいを繊細に表す語彙や、感情のゆらぎをすくい取る柔らかな表現。
そして、あえて曖昧にすることで相手を思いやる独特の言い回し。
そうした言葉の豊かさに、何度も助けられてきました。
けれども、その「日本語が好き」という気持ちが、誰かをジャッジするための物差しになってはいけない。
日本語を大切にすることと、他者に寛容であることは、両立できるはず。
あなたは、どう思いますか?
「言葉を大切にする」とは、どのようなことなのでしょうか。
そして、「正しい日本語」とは、本当に誰のものなのでしょうか。

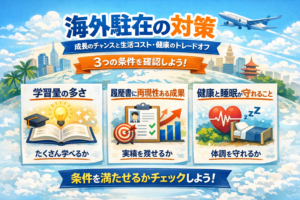


コメント